>> 鴨方遠隔授業ホームページ
惑星の気象学
[2週目 後半]
小高 正嗣(北大院理・地球惑星科学専攻助手)
odakker@gfd-dennou.org
2002 年 10 月 30 日
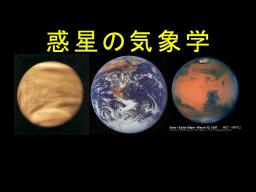
|
地球型惑星のうち, 大気をもつ金星・地球・火星の気象を取り上げます.
|
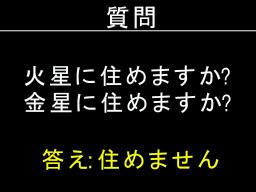
|
地球の隣の惑星, 金星・火星に, 人は住めると思いますか?
実は, どちらの星でも無理なのです. 火星は温度が低いのを
がまんしても, 気圧が地球の 1/100 程度しかないので,
私達は体を維持することができません. 金星は表面気温が
500 ℃ 近くもあるので, こちらもだめです.
|
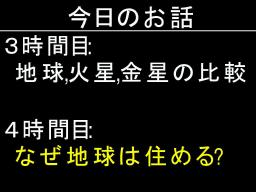
|
後半の講義では, それならばどうして私達は, 地球に住めるのか
考えていくことにしましょう.
|
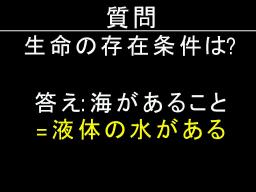
|
ところで, 生物が存在できるために必要な物は何でしょう?
呼吸のための酸素, 光合成のための太陽エネルギーも考えられますが,
地球で初めに誕生した生物は酸素がなくても平気な, 光合成を行なわない
生物だったとされています. しかしそんな彼らも, 海があったから
誕生したと考えられています. 液体の水が重要なのです!
|
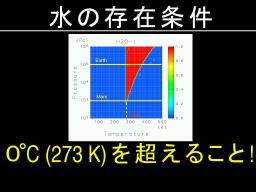
|
こちらの図はどのような温度・圧力ならば, 液体の水が存在できるのかを
表しています. 横軸には温度, 縦軸には圧力がとってあります.
橙色の線はそれぞれ, 火星と地球の表面気圧を表しています.
この図から, 液体の水が存在するためには,
0 ℃(絶対温度で 273K)を越えることが重要だといえます.
|
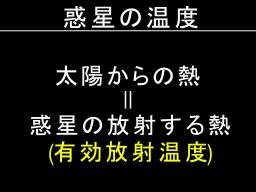
|
ここで, 惑星の温度はどのようにして決まるのかを考えてみましょう.
太陽は惑星よりも高温なので, 惑星は太陽からエネルギーをもらうことは
想像できますね? こうして太陽からのエネルギーを受けながら惑星が
同じ温度を保つためには, 惑星から熱が出ていかなくてはなりません.
こうして, 惑星が得る熱と惑星が失う熱が
釣りあっていると考えた時に決まる惑星の温度を,
有効放射温度といいます.
|
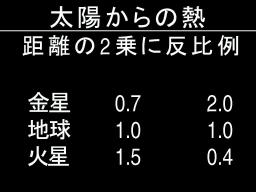
|
それではまずは惑星が得る熱をみてみましょう. 太陽から受けるエネルギーは,
太陽からの距離の2乗に反比例します. 表の左列の数字は, 太陽-地球間の距離を
1としたときの, 太陽-各惑星間の距離を示しています. そしてそれぞれの惑星が
太陽から受ける熱は, 右列の数字で, これも地球を1として示してあります.
金星は地球の2倍の熱を太陽から受けていることがわかります.
|
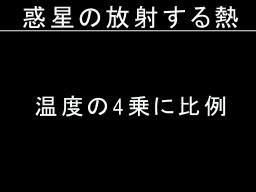
|
今度は惑星から出ていく熱を考えましょう. 惑星が放射によって失う熱は,
惑星の温度の4乗に比例します. 惑星の温度が高いほど, 宇宙に向けて
放出される熱も多くなります.
|
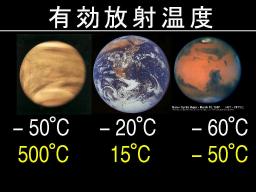
|
上のような考え方で求められた有効放射温度を白, 実際の惑星の温度を
黄色で示してあります. 地球は 35 ℃ ずれていますし, 金星は全く違う温度
ですよね?どうしてこのような差が出てくるのでしょうか?
|
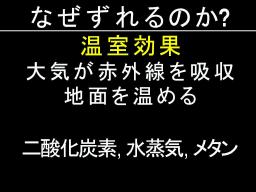
|
実は惑星を取り巻く大気によって, 実際の惑星の温度はもっと高くなって
いるのです. 太陽は高温なので波長の短い電磁波を出し,
そのエネルギーを惑星は受けています. これに対し, 温度の低い惑星は,
波長の長い電磁波(赤外線)を宇宙空間へ放出して冷えています.
二酸化炭素や水蒸気などの気体は, 地球から出ていこうとする赤外線をよく
吸収します. そしてその分, 大気や惑星表面の温度は高くなります.
この大気が惑星の温度を上げる働きは, 一般に
温室効果と呼ばれています.
|

|
こうして温室効果が働き, 高くなった惑星の温度を再び見てみましょう.
金星ではこんなに温室効果が働いているのでしょうか?
地球の温度は液体の水が存在できる程度まで上昇しました. 適度な
温室効果です. そして火星ではほとんど温室効果がないことが
わかります. 惑星間でなぜこのように開きがでてくるのでしょうか?
|
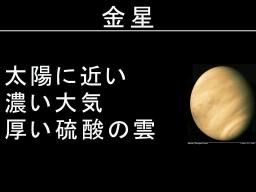
|
金星は太陽に近いため, 地球に比べるともともと受け取る太陽放射の
量は多くなります. 大気がなければ太陽にあたためられて高温になった
分, 宇宙空間へも沢山の放射を出してもっと表面温度が下がる
はずです. ところが金星の二酸化炭素を主成分とする大気はとても厚いため,
金星から出ていく放射は少なくなります. 金星の雲は硫酸でできて
いますが, この硫酸の雲も温度を上げる働きをします.
|
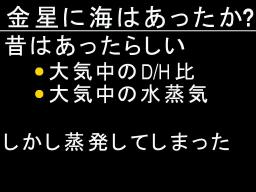
|
生命の誕生に必要な液体の水, 海は金星にもあったのでしょうか?
専門的な話になりますが, 大気中の水素の同位体比, また金星大気に
含まれる微量の水蒸気から, 昔は金星にも海が存在したようです.
しかし温室効果が強すぎたために海の水はどんどん蒸発し,
水蒸気は原子に分解されて宇宙空間へ散逸してしまったと
考えられています.
|
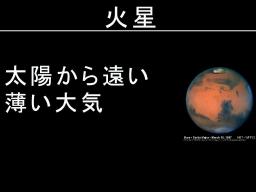
|
次に火星について見てみましょう.
火星は太陽から遠いため、受け取る放射量がもともと少なくなります.
また火星大気は, 温室効果気体である
二酸化炭素が主成分ですが, 大気の量が少ないために少ししか地表温度は
上がりません.
|
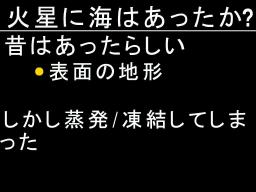
|
温室効果のあまり働かない火星には, 海は存在したのでしょうか?
火星表面の地形から, 昔はあったといわれています.
しかし水は蒸発したか, 凍って地下に氷として存在しているかの
どちらかだろうと考えられています.
|
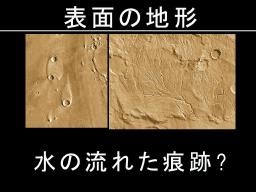
|
それでは海があった証拠と考えられる, 火星表面の地形を見てみましょう.
左側は洪水の跡のように見えます. 中央の中洲のような地形に注目して
下さい. 写真の下から上へ向かって, 水が流れたように見えます.
いくつか見られる丸いくぼみはクレーターです.
右の写真はもっと広い場所について見たものです.
樹形図あるいは網目のような地形がありますね?河川によく似ています.
火星にはこのような地形がいくつもあるため、昔の火星には海が
あったと考えられています.
|
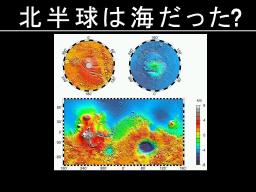
|
こちらは, 火星表面の高度についての観測データを図で表した
ものです. 四角の図は縦軸が緯度(上が北, 下が南), 横軸が
経度です. 赤〜灰色が高度の高い場所, 青にいくにつれて高度が
低い場所を表します. これを見ると南半球ではオレンジ〜赤色で
高度が高くなっています. 対照的に北半球では大部分が
青色で低地となっており, 高度の変化もあまりありません.
これは昔, 北半球に海があり, 表面のでこぼこが削りとられた
ために平らなのではないかと考えられています.
上の円状の図は, 左が南極付近, 右が北極付近の様子を示しています.
|
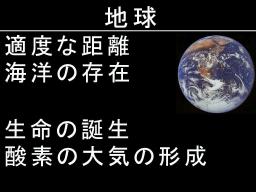
|
最後に地球を見てみましょう.
地球は金星や火星の中間の, 太陽から
ちょうどよい距離に位置しています. 地球には現在も液体の水,
海があります.
地球では長い間, 海を維持することができたため, 海の中で生命が
誕生し, やがて光合成をおこなう生命が生まれ, やはり長い時間を
かけて酸素の多い大気が作られました. このような歴史があって,
私達は今, 地球上で生きているのです.
|
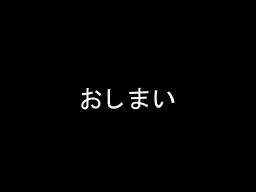
|
これで惑星の気象学の講義はおしまいです.
質問が二つ出されました.
Q. 金星・火星にはオゾン層はありますか?
A. ありません. 金星や火星の大気には, オゾンの材料である
酸素がほとんど存在しないからです.
Q. 火星には季節がありますか?
A. あります. 火星の自転軸は公転面に対してちょうど地球と
同じくらい傾いています. したがって火星にも四季
(季節)があります.
|
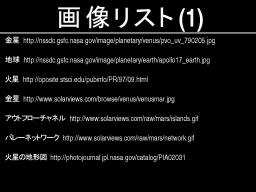
|
このスライドで用いた画像は, 次の場所から入手したものです.
|
Kuniko Egawa
2003-04-25
|